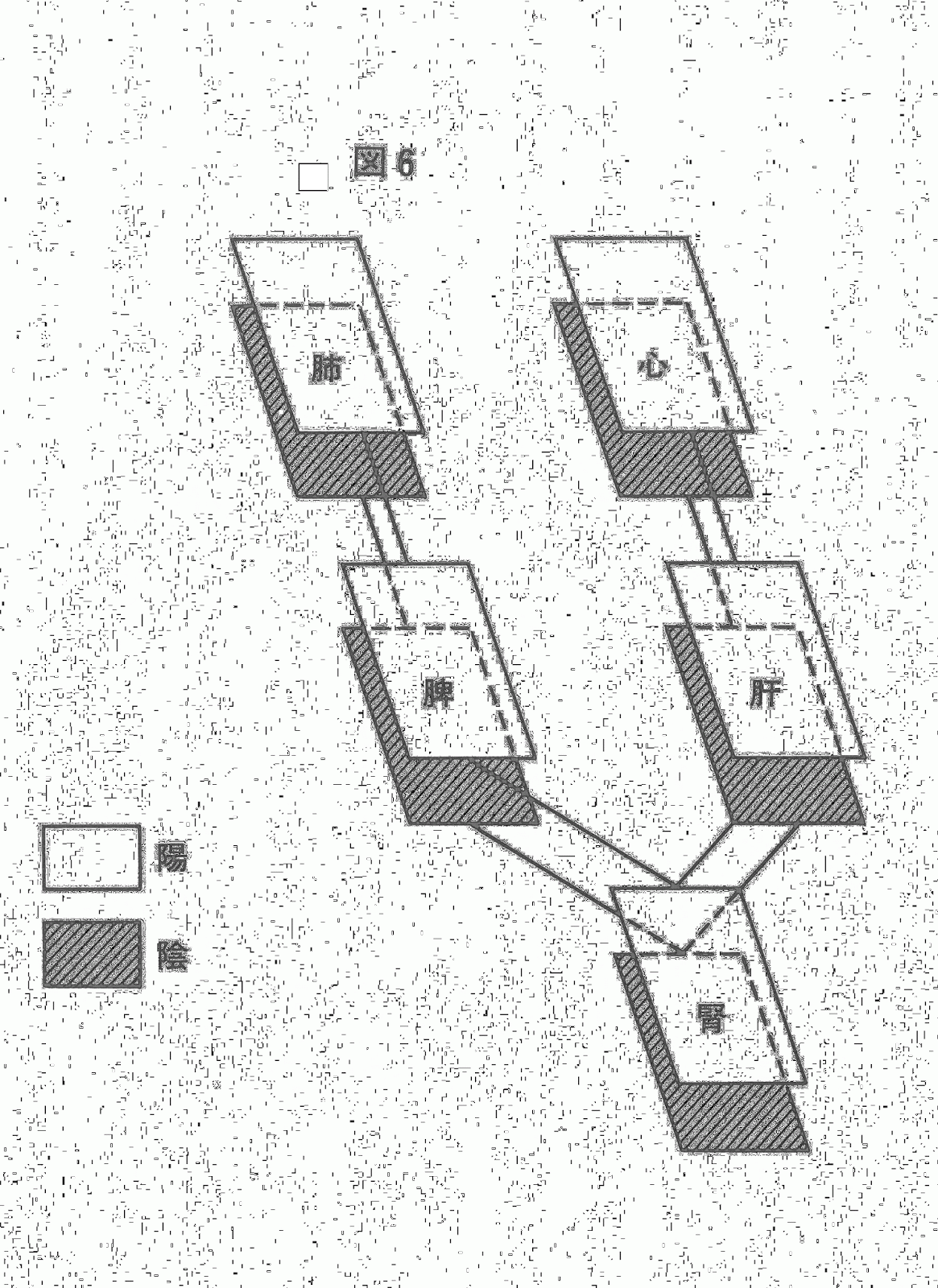13 下焦の疾患
下焦が虚したり、実したりするために起こる疾患に用いられる。ここでは、下焦が虚したために起こる各種疾患に用いられる八味丸(はちみがん)、下焦が実したために起こるものに用いられる竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)についてのべる。
(2)六味丸(ろくみがん)
〔八味丸から桂枝と附子を去ったもの〕
八味丸證に似ているが、小児や妊婦などで陰証と決めにくい場合に用いられる。
『和漢薬方意辞典』 中村謙介著 緑書房
六味丸(ろくみがん) [小児方訣]
【方意】 腎の虚証による精力減退・多尿・腰痛・陰痿・疲労倦怠等と、熱証・燥証による顔面紅潮・心煩・不眠・口渇・発熱等のあるもの。
《太陰病または少陽病.虚実中間から虚証》
【自他覚症状の病態分類】
【脈候】 沈細数。
【舌候】 紅舌、褐色苔を認める。
【腹候】
【病位・虚実】 腎の虚証は太陰病に相当するが、熱証・燥証は陽証であり、本方は少陽病位でも用いる。
虚実中間から虚証である。
【構成生薬】 地黄8.0 山茱萸4.0 山薬4.0 牡丹皮3.0 沢瀉3.0 茯苓3.0
【方解】 本方は丸味丸より桂枝・附子の大熱薬を去ったものであるために、寒証の傾向が少なく、検に熱証を帯びる。
【方意の幅および応用】
A 腎の虚証・熱証・燥証:精力減退・多尿・腰痛・顔面紅潮等を目標にする。
精力減退、遺精、腰痛、糖尿病、慢性腎炎、夜尿症、るいそう
【症例】 視力低下
眼がほとんどみえなくなった患者さん。この病人は帝大に行っていましたが、初めは視神経萎縮といわれ、次には硝子体に何か混濁があるといわれたらしいですが、症状としては他には別に何もいうところはないのです。診断はハッキリしません。私も処方するに捉えどころがないんです。しかし或は腎臓による視神経障碍だろうと思って、大体目がかんすて新聞など読めないという版うな者には六味丸或いは八味丸をこれまでよくやっていましたので、六味丸加減(本方去沢瀉加生地黄・五味子・当帰)を与えましたら、その患者は眼がみえて来たというんです。それからどうも性生活がうまくいかないような事をいうんです。そこで私は今の薬はその点が目標だといったのですが、患者は漢方ほ薬は恐ろしいものだといってしきりに感心していました。
それから面白いことに、その患者が田舎へ帰った時、腎臓の悪い人があって西洋医者の治療で浮腫がとれず困っていたのを、自分の持っていた薬を素人考えで飲ませたら、むくみも取れて良くなったと大気焔をあげていました。
矢数道明 『漢方と漢薬』 7・12・18
萎縮腎による高血圧症
患者は69歳の婦人。かつて尿毒症様の発作を起こしたとき紫円で救ったことがある。患者は防風通聖散の条件を備えており、萎縮腎に因る高血圧である。
尿の出が悪く、肩が凝り、脚がつると訴える。これに防風通聖散に六味丸を兼用した。夜寝ると咽喉がカラカラに乾く。これは萎縮腎の特徴であるが、その場合には六味丸が効くので兼用したのである。以後引き続き2年間服薬を続けているが非常に調子良く回復し、血圧は200mmHgから150mmHgに下り、1日も休まずに済んでいる。
矢数有道 『漢方と漢薬』 7・12・18
肺結核症
18歳、女性。3ヵ月程前より、肺結核と診断され、人工気胸とその他の治療を受けたが一向に良くならず、るいそうが日に加わり、咳嗽、倦怠、発熱等の主訴で来院した。月経も3ヵ月以来ない。寝汗が時にある。食欲と消化はまだ良い。咽喉が乾きやすく凉性飲食を好む。便通は普通1回あるが時には軟便をみる。咳嗽が激しく痰も多い。午後の熱発に際してよく悪寒を感じる。非常に痩せていて栄養が悪いが、顔色は興奮したように両頬が幾分紅潮している。脈は弦数で120位ある。胸部所見は左側の肺尖部より鎖骨下部まで少し悪い。心音は強く亢進している。腹部には著変がないが心下部に軽度の悪痛を有す。
陰虚火動の証であるが、脈が頻数であるのと栄養が悪いのがどうも心配だが、まず補陰潤肺させるつもりで六味湯を加減して(熟地黄8.0 山薬・白芍薬各6.0 麦門冬・白茯苓・牡丹皮・沙参各4.0、桔梗・陳皮各2.1 五味子・甘草各2.0。以上1包、1日2包)与えた。
1週間後に来院、咳嗽は大分軽くなり、気分が大変良いという。便通が少し軟らかい。その後症状に依り本方に黄柏、山茱萸、白扁豆、乾地黄等を加減して約1ヵ月間続服させたら、熱も咳嗽も、脈状も好転し、栄養が段々良くなった。
大山景弘 『漢方と漢薬』 10・10・40
『漢方後世要方解説』 矢数道明著 医道の日本社刊
p.27
補養の剤
方名及び主治
一 六味地黄丸(ロクミジオウガン) 銭仲陽 補陰剤
○肝腎不足、真陰虧損(きそん)し、精血枯渇し、憔悴羸弱(ショウスイルイジャク)し、腰痛足酸(イタミ)、自汗盗汗し、汗水泛(ウカ)んで痰となり、発熱咳嗽し、頭重目眩、耳鳴耳聾、遺精便血、消渇淋瀝(リンレキ)、失血失音、舌燥喉痛し、虚火牙痛足跟(コン)痛をなし、下部瘡瘍等の症を治す。
処方及び薬能
熟地黄、山茱萸、山薬各四
茯苓 丹皮、沢瀉各三
蜜丸空心時塩湯にて服す。冬は酒にて服用す。
熟地=陰を滋し、腎を補い、血を生じ、精を生ず。君薬。
山茱=肝を温め、精を濇らす。
牡丹=君相の伏火(心火、肝火、命門火)を瀉し、血を涼しうす。
山薬=脾を補し、腎を固うす。
茯苓=脾火の湿熱を滲し。
沢瀉=膀胱の水邪を瀉し、耳目を聡明にす。
(2)六味丸(ろくみがん)
〔八味丸から桂枝と附子を去ったもの〕
八味丸證に似ているが、小児や妊婦などで陰証と決めにくい場合に用いられる。
『和漢薬方意辞典』 中村謙介著 緑書房
六味丸(ろくみがん) [小児方訣]
【方意】 腎の虚証による精力減退・多尿・腰痛・陰痿・疲労倦怠等と、熱証・燥証による顔面紅潮・心煩・不眠・口渇・発熱等のあるもの。
《太陰病または少陽病.虚実中間から虚証》
【自他覚症状の病態分類】
| 腎の虚証 | 熱証・燥証 | |||
| 主証 | ◎精力減退 ◎多尿 遺尿 ◎腰痛 下肢痛 ◎陰痿 遺精 | ◎顔面紅潮 ◎心煩 不眠 ◎口渇 口燥 | ||
| 客証 | 疲労 弱視 目眩 耳鳴 るいそう | 発熱 手足煩熱 ほてり 自汗 盗汗 |
【脈候】 沈細数。
【舌候】 紅舌、褐色苔を認める。
【腹候】
【病位・虚実】 腎の虚証は太陰病に相当するが、熱証・燥証は陽証であり、本方は少陽病位でも用いる。
虚実中間から虚証である。
【構成生薬】 地黄8.0 山茱萸4.0 山薬4.0 牡丹皮3.0 沢瀉3.0 茯苓3.0
【方解】 本方は丸味丸より桂枝・附子の大熱薬を去ったものであるために、寒証の傾向が少なく、検に熱証を帯びる。
【方意の幅および応用】
A 腎の虚証・熱証・燥証:精力減退・多尿・腰痛・顔面紅潮等を目標にする。
精力減退、遺精、腰痛、糖尿病、慢性腎炎、夜尿症、るいそう
【参考】*腿の方は『金匱』八味丸の桂枝・附子を去ったものであるから、八味丸よりは軽症である。腎虚のため疲労感があり、特に精力弱く、陰痿・遺精・腰痛等を訴え、多尿・耳鳴・弱視・口渇等を伴うものに用いる。脾虚・気虚著しくして食欲不振・下痢の向向のあるものは禁忌である。
『漢方後世要方解説』
『漢方後世要方解説』
【症例】 視力低下
眼がほとんどみえなくなった患者さん。この病人は帝大に行っていましたが、初めは視神経萎縮といわれ、次には硝子体に何か混濁があるといわれたらしいですが、症状としては他には別に何もいうところはないのです。診断はハッキリしません。私も処方するに捉えどころがないんです。しかし或は腎臓による視神経障碍だろうと思って、大体目がかんすて新聞など読めないという版うな者には六味丸或いは八味丸をこれまでよくやっていましたので、六味丸加減(本方去沢瀉加生地黄・五味子・当帰)を与えましたら、その患者は眼がみえて来たというんです。それからどうも性生活がうまくいかないような事をいうんです。そこで私は今の薬はその点が目標だといったのですが、患者は漢方ほ薬は恐ろしいものだといってしきりに感心していました。
それから面白いことに、その患者が田舎へ帰った時、腎臓の悪い人があって西洋医者の治療で浮腫がとれず困っていたのを、自分の持っていた薬を素人考えで飲ませたら、むくみも取れて良くなったと大気焔をあげていました。
矢数道明 『漢方と漢薬』 7・12・18
萎縮腎による高血圧症
患者は69歳の婦人。かつて尿毒症様の発作を起こしたとき紫円で救ったことがある。患者は防風通聖散の条件を備えており、萎縮腎に因る高血圧である。
尿の出が悪く、肩が凝り、脚がつると訴える。これに防風通聖散に六味丸を兼用した。夜寝ると咽喉がカラカラに乾く。これは萎縮腎の特徴であるが、その場合には六味丸が効くので兼用したのである。以後引き続き2年間服薬を続けているが非常に調子良く回復し、血圧は200mmHgから150mmHgに下り、1日も休まずに済んでいる。
矢数有道 『漢方と漢薬』 7・12・18
肺結核症
18歳、女性。3ヵ月程前より、肺結核と診断され、人工気胸とその他の治療を受けたが一向に良くならず、るいそうが日に加わり、咳嗽、倦怠、発熱等の主訴で来院した。月経も3ヵ月以来ない。寝汗が時にある。食欲と消化はまだ良い。咽喉が乾きやすく凉性飲食を好む。便通は普通1回あるが時には軟便をみる。咳嗽が激しく痰も多い。午後の熱発に際してよく悪寒を感じる。非常に痩せていて栄養が悪いが、顔色は興奮したように両頬が幾分紅潮している。脈は弦数で120位ある。胸部所見は左側の肺尖部より鎖骨下部まで少し悪い。心音は強く亢進している。腹部には著変がないが心下部に軽度の悪痛を有す。
陰虚火動の証であるが、脈が頻数であるのと栄養が悪いのがどうも心配だが、まず補陰潤肺させるつもりで六味湯を加減して(熟地黄8.0 山薬・白芍薬各6.0 麦門冬・白茯苓・牡丹皮・沙参各4.0、桔梗・陳皮各2.1 五味子・甘草各2.0。以上1包、1日2包)与えた。
1週間後に来院、咳嗽は大分軽くなり、気分が大変良いという。便通が少し軟らかい。その後症状に依り本方に黄柏、山茱萸、白扁豆、乾地黄等を加減して約1ヵ月間続服させたら、熱も咳嗽も、脈状も好転し、栄養が段々良くなった。
大山景弘 『漢方と漢薬』 10・10・40
『漢方後世要方解説』 矢数道明著 医道の日本社刊
p.27
補養の剤
方名及び主治
一 六味地黄丸(ロクミジオウガン) 銭仲陽 補陰剤
○肝腎不足、真陰虧損(きそん)し、精血枯渇し、憔悴羸弱(ショウスイルイジャク)し、腰痛足酸(イタミ)、自汗盗汗し、汗水泛(ウカ)んで痰となり、発熱咳嗽し、頭重目眩、耳鳴耳聾、遺精便血、消渇淋瀝(リンレキ)、失血失音、舌燥喉痛し、虚火牙痛足跟(コン)痛をなし、下部瘡瘍等の症を治す。
処方及び薬能
熟地黄、山茱萸、山薬各四
茯苓 丹皮、沢瀉各三
蜜丸空心時塩湯にて服す。冬は酒にて服用す。
熟地=陰を滋し、腎を補い、血を生じ、精を生ず。君薬。
山茱=肝を温め、精を濇らす。
牡丹=君相の伏火(心火、肝火、命門火)を瀉し、血を涼しうす。
山薬=脾を補し、腎を固うす。
茯苓=脾火の湿熱を滲し。
沢瀉=膀胱の水邪を瀉し、耳目を聡明にす。
解説及び応用
○此方は金匱八味丸の桂枝、附子を去ったものであるから、八味丸よりは軽症である。腎虚のため疲労感があり、特に精力弱く、陰萎、遺精、腰痛等を訴え、多尿、耳鳴、弱視、口渇等を伴なうものに用いる。脾虚、気虚著しくて食欲不振、下痢の傾向あるものは禁忌である。
○応用
① 性的衰弱で陰萎、遺精、耳鳴を訴え根気なきもの ② 初老以後の者で腰痛、眼精疲労、視力減退するもの ③ 糖尿病にて虚状を呈し、陰萎、多尿、口渇するもの ④ 慢性腎炎、萎縮腎にて疲労、多尿のもの ⑤ 夜尿症にこの方の効あるものがある。 ⑥筋骨萎弱のもの。
『漢方一貫堂の世界 -日本後世派の潮流』 松本克彦著 自然社刊
p.295
六味丸をめぐって
ここでは腎を中心にした図を紹介したが、以前坂口弘先生は脾を中心にしたシェーマを考えておられ、これが中医学と(日本の)後世派との主な相違点であるような感じを受けている。
この腎を基本とする考え方は中国でも比較的新しく、『素問』でも脾土が中央という言葉は見掛けるが、腎を中心とするとは述べられていないようで、金元医学の大家李杲(東垣)が著した『脾胃論』においても、あくまで脾を中心に考えられているようである。先天を主にするか後天を主にするかという議論にもなろうが、臨床の上でも、多くの疾患のベースには気虚・脾虚があるようで、治療上脾を中心にするということもやはり大きな意味がある。結局は五臓間の相関性を重視する医学であるから、五行をぐるりと回せばどれを基本にしてもよいのかも知れない。中島紀一先生が八味丸や六味丸を使われたのを見たことがないため、以前そのことをお伺いしたところ、「竜胆瀉肝湯(清肝袪湿)は六味丸(補腎陰)と同じですから、両方使う必要はありません」とのことであった。まったく薬味と方意の違うこの両者の共通性についてその考えつづけているが、事実、臨床の上で六味丸を使感たいような患者に竜胆瀉肝湯を使ってよい結果を得ることも多く、結局腎陰を補うのも(六味丸)、肝陽を瀉すのも(竜胆瀉肝湯)、結果として同じことで、更に竜胆瀉肝湯には下焦に対する処置(木通-膀胱、車前子-腎)もしてあると解釈している。つまりは本当の意味で漢方の生理病理が分れば、それ程新しい薬方を使わずとも、またどこから治療していってよいのかも知れず、理論にしてもあまり枝葉に入りすぎると、かえって机上の空論に陥る危険性もあろう。
臓腑の陰陽
しかしながら腎を中心にして、さらには各臓腑をすべて陰陽に分けて考えるという方法は、最近の中国では次第に統一されてきているようなので、ここで彼等の考えている腎、さらに陰陽というものについて今少しのべてみたい。
即ち前節では主に気血の関係から大きく陰陽を左右に分けたが、今回さらに軸を九〇度回転させ、前後から見て各臓腑を陽の側面と陰の側面に分け、そのベースとして腎陰と腎陽を考えるのである。(図6参照)。
即ち各臓腑をさらにそれぞれの機能的な側面(陽)と物質的な側面(陰)とに分ければ、各々のもつ生理的、病理的な意味づけ、および対する薬剤も一層はっきりとし、理論的にも臨床的にもより整備された形になるであろう。
このような個々の臓腑の陰陽、引いては腎の陰陽の考え方は決して一朝一夕にできたものではない。そもそもの源は、傷寒・金匱の薬方の中にも求められようが、中医学の教科書によれば、「この発想の起源は唐の王冰に始まり、確立されたのは明の張介賓においてである」と書かれている。したがって金元医学を主とする日本の後世派の処方集にも六味丸等の名前は散見されるが、理論的には充分消化されていないのは当然といえよう。この明代における陰陽に対する考え方の新たな展開は、この時代に現れた温病学の理論とも切り離せないように思われる。すなわち『傷寒論』に述べられている傷寒の経過は、あくまで寒という陰邪に陽を侵害されて引き起こされたものであるため、最終的には回陽という治法に帰するのに対し、温病は温熱という陽邪に起因するので、どうしても陰(体液)を消耗しやすく、一貫して補陰という手法が大きなウェートを占めることになり、ここに補陽と補陰の二大補法の原則が確立されたといえよう。
補陰と補陽
さて補陰・補陽について述べる前に、今一度気・血、寒・熱と陰陽の関係をまとめ見たい。
前に説明した図は平面であったため、津液と血が左右に分かれ、少し意味のとりにくい点もあったようだが、気の津液および血は相互に関連、一部は重復し合い、立体的にはこの図(図7参照)のようになるかと思われる。私の個人的な見解では、この重復は気と津液の間が一番大きく、以下津液と血、血と気の順になるのではないかと考えている。
以前坂口先生が「気血に寒熱をからませたのが面白かった」といわれたが、実はこの関係は、山本巌先生が「気虚に寒が加わったものが陽虚だ」といっておられたのにヒントを得たもので、この図を北京の中医に見せたところ、「これ程単純ではないが、原則的には宜しい」とのことであった。
すなわち陰陽を考える上では、前に述べた気・血および津液以外に寒と熱とが非常に重要で、陽を補うには補気剤に熱性の薬味を加えることが多く、前に述べた十全大補湯の黄耆(益気)、桂枝(温陽)の組み合わせなどもその例であろう。またこれとは逆に、補陰には滋潤剤と寒性をまった薬物の組み合せ、例えば白虎加人参湯に知母(滋養・清熱)と石膏(清熱・瀉火)等が用いられているのもこのことを物語っている。一方一つの薬物は多種の薬効をもち、目的によっては陰陽相反する場合もしばしばあり、例えば人参は補気(補陽)の作用と同時に生津(補陰)の作用があるため、補気に重点を置くには茯苓を加えて利水をする。また補剤ではないが、三黄といわれる黄連、黄芩、黄柏等には寒(陰)の作用とともに燥(陽)の作用があり、この燥性は陰(血液・津液)を傷害するため、当帰、地黄等の滋潤剤を加えてこの作用を緩和させる。このように、目的によって各薬味の欠点を補い、長所をのばそうという処方上の組み合せはよく見られる。
六味丸の構成
六味丸は正しくは六味地黄丸(『小児薬証直抉』:宋)といい、宋代に作られた処方である。後漢に工夫された八味丸(『金匱要略』:後漢)から桂枝と附子とを取り除いただけのものであるが、この間、数百年の年月が流れており、やはり唐代に腎陰の概念が出されてから独立した処方とする必然性が生じたように思われる。
この処方は、肝、腎、脾三組の補瀉を組み合わせた名方といわれるが、構成する薬味の主な薬効と帰経は表1のとおりである。
各薬味の上に書いたのが薬効、下が帰経で、主とするものに丸印を付けた。上の段はいずれも補剤で各臓の陰を補い、下段は各々に対する瀉と考えられる。また( )内は薬性であるが、全体的にみると寒熱相半ばし、いわゆる平と考えられ、この処方がいかにすべてに渉ってよくバランスが考えられているかが分る。このようにこの処方は広く三臓の陰を補う処方ではあるが、同時に各薬味はすべて腎とも関連をもち、さらに主薬の熟地黄の量は山薬、山茱萸の倍で、やはり基本的には補腎を目的にしたものといえよう。この処方を見ていると、広く他臓と関連を持つ腎という概念が分ってくるような気もするが、同時に臨床的にあらゆる慢性消耗性疾患に対する基本方として、「久服して安全だ」といわれる意味も理解される。ただバランスがとれすぎて焦点がぼやけるせいか、やや効果が緩慢にすぎ、このため実際応用する際には各種の加減方が工夫されている。また方剤学の本には原方を用いる場合でも、「例えば水腫に対しては茯苓・沢瀉の比率を増すとか、その時の状況によって加減するのがよい」と述べられており、またあくまで方意が大切なので、「個々の薬味自身は地黄は何首烏に替え、あるいは山茱萸を牛膝や女貞子に替える等、適宜置き替えてもよい」とのことである。
また余談になるが、熟地黄や山薬等粘膩の薬物は痰湿の多い患者には胸に痞えることが多く、対策としては陳皮や砂仁を加えることもあるが、また丸にする方が湯液としてより飲みやすいともいわれている。
金匱腎気丸(附桂八味丸)と知柏地黄丸(知柏八味丸)
いわゆる八味丸は『金匱要略』には崔氏八味丸・八味腎気丸(円)および腎気丸(円)という名称で、それぞれ中風歴節風、血痺虚労病と婦人雑病の章に記載されているが、最近の中国では金匱腎気丸という名で呼ばれていることが多い。また現在中国では桂枝と肉桂とは区別され、桂枝の代りに肉桂を用いたものは附桂八味丸と呼ばれるようである。しかし漢代にはこの区別はなく、現在日本ではすべて肉桂が用いられている。ご参考までに中草薬学書による両者の薬効の違いをあげておいて(表2参照)。
いずれにしても桂・附の組み合わせは温熱剤の代表的なもので、この組み合わせを寒熱の上で平である六味丸に加えて温性(陽性)を付加したものである。
さて六味丸は前にも述べたように、もともとは腎陰の補剤といわれ、用いられている薬味もすべて補陰の剤から成っている訳で、これに温性を加えただけの八味丸が腎陽の補剤といわれるのは、少し合点がいかない気もする。前に伊藤良先生が「八味丸はあくまで腎気を補うもので、腎陽を補うとはいえないのではないか」と言っておられたが、このことを指しておられたように思われる。方剤学の本には、腎陰と腎陽とは密接な関係があり、もともとは一つのものである。即ちよく陽を補おうとすればまず陰を補わねばならない。」という風に書かれているが、一口に機能とか物質とかいっても、物質を離れた機能はあり得ず、また生体のすべての物質は何等かの意味で機能に関係しているわけで、陰陽の関係も単純には割り切れないようである。しかし、以上から考えると正確には陰陽双補の剤といった方がより適切なのかもしれない。
さて金匱腎気丸に対してとりあげたいものに知柏地黄丸(『医宗金鑑』:明)、別名を知柏八味丸というのがあり、比較しながら考えてみたいと思う。知柏地黄丸は六味丸が独立した処方となってからさらに数百年たち、明の時代になって滋陰清熱の概念が確立されてから工夫されたものであるが、内容は表3のような構成である。
知母・黄柏はともに代表的な寒剤で一方は潤性、一方は燥性をもち、またともに腎に入るといったことからもよく用いられる組み合わせで、いろいろな処方の中に見うけられる。この二つの寒剤の組み合わせで、いわゆる命門の火(腎陽)を抑え、六味丸の補陰効果と合わせて陰虚陽亢に対そうとするもので、ある意味では金匱腎気とはまったく正反対の意図をもっている。私はこれをベーチェット病の安定期に入ったものや、糖尿病で熱症が顕著なものによく用いているが、その際は熟地黄(補血、補腎) (微温)を生地黄(滋陰清熱) (寒)即ち乾地黄に変えている。
中島先生は知母の使用には非常に慎重で、おそらくリュウマチ患者に桂芍知母湯を使われたのだと思うが、「水腫を助長し病状を悪化させたことがある」と何回も注意を受けた。代表的な寒剤で且つ生津作用をもつのであるから、こういうケースも当然考えられ、八味丸と知柏地黄丸がいづれも広く用いられている今日、漢方の薬理に対する知識と正しい使い方は早く普及させる必要があろう。
その他の加減法
この他にも六味丸を基とした処方は明清以後多く工夫されているが、そのうちもっとも代表的なものだけをいくつかとり上げてみたいと思う。(表3参照)
(1) 杞菊地黄丸(『医級』:清)
枸杞子、菊花はいずれも明目の作用があり、 眼病、眼精疲労等にもよく用いられる。しかしこの二味が処方にとりいれられているより重要な意味合いは、枸杞子の下焦すなわち体の下部に対する補に対し、菊花は頭目、即ち体の上部に対する清熱で、いわゆる陰虚による虚火上炎・上実下虚の病証に対して考案されたものと思われる。この処方は中国で現在各種の疾患に広く用いられているが、例えば高血圧による頭痛等にも、速効性は期待できないが、久服しているとよい場合が多い。
(2) 麦味地黄丸(『医級』:清)
六味丸に五味子を加えたものを七味都気丸といってよく端息に用いるが、これにさらに麦門冬を加えたもので八仙長寿丸とも呼ばれている。この麦門冬、五味子という組み合わせは生脈散(『内外傷弁惑論』:金):人参、麦門冬、五味子から出たものと思われるが、ご覧のように麦門冬、五味子はいずれも上焦(心・肺)に対する滋潤作用があり、六味丸の巾を上に広げたものと思われる。なおここで五味子のもつ収斂作用というのは、例えば汗や咳を収めて下痢を止める等の効果をいうが、一種の保護緩衝作用ではないかと思われる。
ご参考までにこの両者の組み合わせを用いた処方をいくつか上げると、清暑益気湯(『弁惑論』:金)、清肺湯(『万病回春』咳嗽門:明)、清熱補気湯および清熱補血湯(証治準縄:明)等で、いずれも清熱と滋陰を兼ねた処方である。
したがって麦味地黄丸は都気丸とともに永くつづいた乾性の咳等に用いられるが、その他知柏地黄丸を用いる程の熱症はないが、上焦の津液欠乏が強く、口が乾く、舌が紅い、舌苔が少い等、老人による見られるような症状があれば咳はなくても使用できる。私も糖尿病等にもよく加減して用いているが、この際も熱症があれば熟地黄を乾地黄に変え、あるいは両者半々にする等工夫している。
(3) 帰芍地黄丸(『中国医学大辞典』:民国)
この処方は前の二つ程有名なものではないが、当帰、白芍に六味丸の熟地黄を合わせれば四物湯から川芎を除いたものとなり、四物湯と六味丸との合方に近いとも考えられる。六味丸に養肝補血の作用を加えたものであるから肝腎陰虚証に広く適用され、例えば慢性肝炎の軟解期待等で、検査成績は大むね正常だがなお陰虚の症状があるといった場合とか、応用範囲の広い方剤なので紹介しておく。
以上いくつかの処方をとり上げたが、前に述べたよ乗に六味丸は方意さえつかめば加減は適当に行えばよいとされており、また成方として他にも柴芍地黄丸、参麦地黄丸、あるいは八味丸を基にした済生腎気丸等いくつもある。
左帰飲(丸)と右帰飲(丸)(『景岳全書』 :明)
最後に明代の名医張介賓(景岳)が、この六味丸・八味丸を基礎に、各々の効果を強めるため、どのように加減しているかを、彼の右帰飲(丸))、左帰飲(丸)をとり上げて一連の表にしてみた。
補腎陰
左帰飲<補>熟地、山薬、山茱萸
<瀉>-、茯苓、-
<加味>甘草
左帰丸<補>熟地、山薬、山茱萸
<瀉>-、-、-
<加味>菟絲子(陽)、鹿角膠(陽)、亀板膠(陰)、枸杞子(陰)、牛膝(陰)
○此方は金匱八味丸の桂枝、附子を去ったものであるから、八味丸よりは軽症である。腎虚のため疲労感があり、特に精力弱く、陰萎、遺精、腰痛等を訴え、多尿、耳鳴、弱視、口渇等を伴なうものに用いる。脾虚、気虚著しくて食欲不振、下痢の傾向あるものは禁忌である。
○応用
① 性的衰弱で陰萎、遺精、耳鳴を訴え根気なきもの ② 初老以後の者で腰痛、眼精疲労、視力減退するもの ③ 糖尿病にて虚状を呈し、陰萎、多尿、口渇するもの ④ 慢性腎炎、萎縮腎にて疲労、多尿のもの ⑤ 夜尿症にこの方の効あるものがある。 ⑥筋骨萎弱のもの。
『漢方一貫堂の世界 -日本後世派の潮流』 松本克彦著 自然社刊
p.295
六味丸をめぐって
ここでは腎を中心にした図を紹介したが、以前坂口弘先生は脾を中心にしたシェーマを考えておられ、これが中医学と(日本の)後世派との主な相違点であるような感じを受けている。
この腎を基本とする考え方は中国でも比較的新しく、『素問』でも脾土が中央という言葉は見掛けるが、腎を中心とするとは述べられていないようで、金元医学の大家李杲(東垣)が著した『脾胃論』においても、あくまで脾を中心に考えられているようである。先天を主にするか後天を主にするかという議論にもなろうが、臨床の上でも、多くの疾患のベースには気虚・脾虚があるようで、治療上脾を中心にするということもやはり大きな意味がある。結局は五臓間の相関性を重視する医学であるから、五行をぐるりと回せばどれを基本にしてもよいのかも知れない。中島紀一先生が八味丸や六味丸を使われたのを見たことがないため、以前そのことをお伺いしたところ、「竜胆瀉肝湯(清肝袪湿)は六味丸(補腎陰)と同じですから、両方使う必要はありません」とのことであった。まったく薬味と方意の違うこの両者の共通性についてその考えつづけているが、事実、臨床の上で六味丸を使感たいような患者に竜胆瀉肝湯を使ってよい結果を得ることも多く、結局腎陰を補うのも(六味丸)、肝陽を瀉すのも(竜胆瀉肝湯)、結果として同じことで、更に竜胆瀉肝湯には下焦に対する処置(木通-膀胱、車前子-腎)もしてあると解釈している。つまりは本当の意味で漢方の生理病理が分れば、それ程新しい薬方を使わずとも、またどこから治療していってよいのかも知れず、理論にしてもあまり枝葉に入りすぎると、かえって机上の空論に陥る危険性もあろう。
臓腑の陰陽
しかしながら腎を中心にして、さらには各臓腑をすべて陰陽に分けて考えるという方法は、最近の中国では次第に統一されてきているようなので、ここで彼等の考えている腎、さらに陰陽というものについて今少しのべてみたい。
即ち前節では主に気血の関係から大きく陰陽を左右に分けたが、今回さらに軸を九〇度回転させ、前後から見て各臓腑を陽の側面と陰の側面に分け、そのベースとして腎陰と腎陽を考えるのである。(図6参照)。
即ち各臓腑をさらにそれぞれの機能的な側面(陽)と物質的な側面(陰)とに分ければ、各々のもつ生理的、病理的な意味づけ、および対する薬剤も一層はっきりとし、理論的にも臨床的にもより整備された形になるであろう。
このような個々の臓腑の陰陽、引いては腎の陰陽の考え方は決して一朝一夕にできたものではない。そもそもの源は、傷寒・金匱の薬方の中にも求められようが、中医学の教科書によれば、「この発想の起源は唐の王冰に始まり、確立されたのは明の張介賓においてである」と書かれている。したがって金元医学を主とする日本の後世派の処方集にも六味丸等の名前は散見されるが、理論的には充分消化されていないのは当然といえよう。この明代における陰陽に対する考え方の新たな展開は、この時代に現れた温病学の理論とも切り離せないように思われる。すなわち『傷寒論』に述べられている傷寒の経過は、あくまで寒という陰邪に陽を侵害されて引き起こされたものであるため、最終的には回陽という治法に帰するのに対し、温病は温熱という陽邪に起因するので、どうしても陰(体液)を消耗しやすく、一貫して補陰という手法が大きなウェートを占めることになり、ここに補陽と補陰の二大補法の原則が確立されたといえよう。
補陰と補陽
さて補陰・補陽について述べる前に、今一度気・血、寒・熱と陰陽の関係をまとめ見たい。
前に説明した図は平面であったため、津液と血が左右に分かれ、少し意味のとりにくい点もあったようだが、気の津液および血は相互に関連、一部は重復し合い、立体的にはこの図(図7参照)のようになるかと思われる。私の個人的な見解では、この重復は気と津液の間が一番大きく、以下津液と血、血と気の順になるのではないかと考えている。
以前坂口先生が「気血に寒熱をからませたのが面白かった」といわれたが、実はこの関係は、山本巌先生が「気虚に寒が加わったものが陽虚だ」といっておられたのにヒントを得たもので、この図を北京の中医に見せたところ、「これ程単純ではないが、原則的には宜しい」とのことであった。
すなわち陰陽を考える上では、前に述べた気・血および津液以外に寒と熱とが非常に重要で、陽を補うには補気剤に熱性の薬味を加えることが多く、前に述べた十全大補湯の黄耆(益気)、桂枝(温陽)の組み合わせなどもその例であろう。またこれとは逆に、補陰には滋潤剤と寒性をまった薬物の組み合せ、例えば白虎加人参湯に知母(滋養・清熱)と石膏(清熱・瀉火)等が用いられているのもこのことを物語っている。一方一つの薬物は多種の薬効をもち、目的によっては陰陽相反する場合もしばしばあり、例えば人参は補気(補陽)の作用と同時に生津(補陰)の作用があるため、補気に重点を置くには茯苓を加えて利水をする。また補剤ではないが、三黄といわれる黄連、黄芩、黄柏等には寒(陰)の作用とともに燥(陽)の作用があり、この燥性は陰(血液・津液)を傷害するため、当帰、地黄等の滋潤剤を加えてこの作用を緩和させる。このように、目的によって各薬味の欠点を補い、長所をのばそうという処方上の組み合せはよく見られる。
六味丸の構成
六味丸は正しくは六味地黄丸(『小児薬証直抉』:宋)といい、宋代に作られた処方である。後漢に工夫された八味丸(『金匱要略』:後漢)から桂枝と附子とを取り除いただけのものであるが、この間、数百年の年月が流れており、やはり唐代に腎陰の概念が出されてから独立した処方とする必然性が生じたように思われる。
この処方は、肝、腎、脾三組の補瀉を組み合わせた名方といわれるが、構成する薬味の主な薬効と帰経は表1のとおりである。
各薬味の上に書いたのが薬効、下が帰経で、主とするものに丸印を付けた。上の段はいずれも補剤で各臓の陰を補い、下段は各々に対する瀉と考えられる。また( )内は薬性であるが、全体的にみると寒熱相半ばし、いわゆる平と考えられ、この処方がいかにすべてに渉ってよくバランスが考えられているかが分る。このようにこの処方は広く三臓の陰を補う処方ではあるが、同時に各薬味はすべて腎とも関連をもち、さらに主薬の熟地黄の量は山薬、山茱萸の倍で、やはり基本的には補腎を目的にしたものといえよう。この処方を見ていると、広く他臓と関連を持つ腎という概念が分ってくるような気もするが、同時に臨床的にあらゆる慢性消耗性疾患に対する基本方として、「久服して安全だ」といわれる意味も理解される。ただバランスがとれすぎて焦点がぼやけるせいか、やや効果が緩慢にすぎ、このため実際応用する際には各種の加減方が工夫されている。また方剤学の本には原方を用いる場合でも、「例えば水腫に対しては茯苓・沢瀉の比率を増すとか、その時の状況によって加減するのがよい」と述べられており、またあくまで方意が大切なので、「個々の薬味自身は地黄は何首烏に替え、あるいは山茱萸を牛膝や女貞子に替える等、適宜置き替えてもよい」とのことである。
また余談になるが、熟地黄や山薬等粘膩の薬物は痰湿の多い患者には胸に痞えることが多く、対策としては陳皮や砂仁を加えることもあるが、また丸にする方が湯液としてより飲みやすいともいわれている。
金匱腎気丸(附桂八味丸)と知柏地黄丸(知柏八味丸)
いわゆる八味丸は『金匱要略』には崔氏八味丸・八味腎気丸(円)および腎気丸(円)という名称で、それぞれ中風歴節風、血痺虚労病と婦人雑病の章に記載されているが、最近の中国では金匱腎気丸という名で呼ばれていることが多い。また現在中国では桂枝と肉桂とは区別され、桂枝の代りに肉桂を用いたものは附桂八味丸と呼ばれるようである。しかし漢代にはこの区別はなく、現在日本ではすべて肉桂が用いられている。ご参考までに中草薬学書による両者の薬効の違いをあげておいて(表2参照)。
いずれにしても桂・附の組み合わせは温熱剤の代表的なもので、この組み合わせを寒熱の上で平である六味丸に加えて温性(陽性)を付加したものである。
さて六味丸は前にも述べたように、もともとは腎陰の補剤といわれ、用いられている薬味もすべて補陰の剤から成っている訳で、これに温性を加えただけの八味丸が腎陽の補剤といわれるのは、少し合点がいかない気もする。前に伊藤良先生が「八味丸はあくまで腎気を補うもので、腎陽を補うとはいえないのではないか」と言っておられたが、このことを指しておられたように思われる。方剤学の本には、腎陰と腎陽とは密接な関係があり、もともとは一つのものである。即ちよく陽を補おうとすればまず陰を補わねばならない。」という風に書かれているが、一口に機能とか物質とかいっても、物質を離れた機能はあり得ず、また生体のすべての物質は何等かの意味で機能に関係しているわけで、陰陽の関係も単純には割り切れないようである。しかし、以上から考えると正確には陰陽双補の剤といった方がより適切なのかもしれない。
さて金匱腎気丸に対してとりあげたいものに知柏地黄丸(『医宗金鑑』:明)、別名を知柏八味丸というのがあり、比較しながら考えてみたいと思う。知柏地黄丸は六味丸が独立した処方となってからさらに数百年たち、明の時代になって滋陰清熱の概念が確立されてから工夫されたものであるが、内容は表3のような構成である。
知母・黄柏はともに代表的な寒剤で一方は潤性、一方は燥性をもち、またともに腎に入るといったことからもよく用いられる組み合わせで、いろいろな処方の中に見うけられる。この二つの寒剤の組み合わせで、いわゆる命門の火(腎陽)を抑え、六味丸の補陰効果と合わせて陰虚陽亢に対そうとするもので、ある意味では金匱腎気とはまったく正反対の意図をもっている。私はこれをベーチェット病の安定期に入ったものや、糖尿病で熱症が顕著なものによく用いているが、その際は熟地黄(補血、補腎) (微温)を生地黄(滋陰清熱) (寒)即ち乾地黄に変えている。
中島先生は知母の使用には非常に慎重で、おそらくリュウマチ患者に桂芍知母湯を使われたのだと思うが、「水腫を助長し病状を悪化させたことがある」と何回も注意を受けた。代表的な寒剤で且つ生津作用をもつのであるから、こういうケースも当然考えられ、八味丸と知柏地黄丸がいづれも広く用いられている今日、漢方の薬理に対する知識と正しい使い方は早く普及させる必要があろう。
その他の加減法
この他にも六味丸を基とした処方は明清以後多く工夫されているが、そのうちもっとも代表的なものだけをいくつかとり上げてみたいと思う。(表3参照)
(1) 杞菊地黄丸(『医級』:清)
枸杞子、菊花はいずれも明目の作用があり、 眼病、眼精疲労等にもよく用いられる。しかしこの二味が処方にとりいれられているより重要な意味合いは、枸杞子の下焦すなわち体の下部に対する補に対し、菊花は頭目、即ち体の上部に対する清熱で、いわゆる陰虚による虚火上炎・上実下虚の病証に対して考案されたものと思われる。この処方は中国で現在各種の疾患に広く用いられているが、例えば高血圧による頭痛等にも、速効性は期待できないが、久服しているとよい場合が多い。
(2) 麦味地黄丸(『医級』:清)
六味丸に五味子を加えたものを七味都気丸といってよく端息に用いるが、これにさらに麦門冬を加えたもので八仙長寿丸とも呼ばれている。この麦門冬、五味子という組み合わせは生脈散(『内外傷弁惑論』:金):人参、麦門冬、五味子から出たものと思われるが、ご覧のように麦門冬、五味子はいずれも上焦(心・肺)に対する滋潤作用があり、六味丸の巾を上に広げたものと思われる。なおここで五味子のもつ収斂作用というのは、例えば汗や咳を収めて下痢を止める等の効果をいうが、一種の保護緩衝作用ではないかと思われる。
ご参考までにこの両者の組み合わせを用いた処方をいくつか上げると、清暑益気湯(『弁惑論』:金)、清肺湯(『万病回春』咳嗽門:明)、清熱補気湯および清熱補血湯(証治準縄:明)等で、いずれも清熱と滋陰を兼ねた処方である。
したがって麦味地黄丸は都気丸とともに永くつづいた乾性の咳等に用いられるが、その他知柏地黄丸を用いる程の熱症はないが、上焦の津液欠乏が強く、口が乾く、舌が紅い、舌苔が少い等、老人による見られるような症状があれば咳はなくても使用できる。私も糖尿病等にもよく加減して用いているが、この際も熱症があれば熟地黄を乾地黄に変え、あるいは両者半々にする等工夫している。
(3) 帰芍地黄丸(『中国医学大辞典』:民国)
この処方は前の二つ程有名なものではないが、当帰、白芍に六味丸の熟地黄を合わせれば四物湯から川芎を除いたものとなり、四物湯と六味丸との合方に近いとも考えられる。六味丸に養肝補血の作用を加えたものであるから肝腎陰虚証に広く適用され、例えば慢性肝炎の軟解期待等で、検査成績は大むね正常だがなお陰虚の症状があるといった場合とか、応用範囲の広い方剤なので紹介しておく。
以上いくつかの処方をとり上げたが、前に述べたよ乗に六味丸は方意さえつかめば加減は適当に行えばよいとされており、また成方として他にも柴芍地黄丸、参麦地黄丸、あるいは八味丸を基にした済生腎気丸等いくつもある。
左帰飲(丸)と右帰飲(丸)(『景岳全書』 :明)
最後に明代の名医張介賓(景岳)が、この六味丸・八味丸を基礎に、各々の効果を強めるため、どのように加減しているかを、彼の右帰飲(丸))、左帰飲(丸)をとり上げて一連の表にしてみた。
補腎陰
左帰飲<補>熟地、山薬、山茱萸
<瀉>-、茯苓、-
<加味>甘草
左帰丸<補>熟地、山薬、山茱萸
<瀉>-、-、-
<加味>菟絲子(陽)、鹿角膠(陽)、亀板膠(陰)、枸杞子(陰)、牛膝(陰)
補腎陽
右帰飲<補>熟地、山薬、山茱萸、肉桂、附子 <瀉>-、-、-
<加味>杜仲(陽)、枸杞子(陰)
右帰丸<補>熟地、山薬、肉桂、附子
<瀉>-、-、-
<加味>鹿角膠(陽)、菟絲子(陽)、途中(陽)、枸杞子(陰)
すなわち六味丸・八味丸から瀉の部分を去り、これにそれぞれ補陰および補陽の薬味を加えている。各薬味の後の(陰) (陽)はそれぞれ補陰、補陽を表わすが、陰陽双補のものは主とする方をとった。そしてここにみられるように、腎陽の補にも決成て補陽剤だけに偏らず、補陰剤を適当に混ぜて、あるバランスを保つよう工夫しており、これが中国における陰陽の考え方だと思われる。
なお飲即ち煎剤より丸剤の方が薬味が多く、より復雑になっているが、このことについて中国では一般に急性病には吸収の早い煎剤を、慢性病には丸剤や膏剤をいわれる練り薬を用いる傾向があり、そして一方、急性病には、大剤といって薬味の種類が少なく、一味一味の量の多いものを用い、慢性病には小剤といって、薬味の種類が多く、一味一味の量の少いものを用いるとされ、これらのことから一般に丸薬には多種の薬味が含まれていることが多いようである。左帰・右帰の飲と丸二組の各々の適用を考える際には、こういった面からの検討も必要なように思われる。
※『小児薬証直抉』? 『小児薬証直訣』の誤りか?
『■重連処方解説(84)』
六味丸(ロクミガン)・牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)
日本東洋医学会評議員 三谷和合
■六味丸・出典・構成生薬
六味丸(ろくみがん)は,地黄(ジオウ),山茱萸(サンシュユ),山薬(サンヤク),牡丹皮(ボタンピ),沢瀉(タクシャ),茯苓(ブクリョウ)の6味からできている処方です。
漢方で使用する薬方のほとんどが,いくつかの生薬の組み合わせによるものです。したがって,こうした薬方の成立過程を考えた時,まず単味生薬の薬効の知識があったはずです。続いて2味の薬効,薬剤の知識があり,さらに3味,4味と加味された薬効の知識があって,漢方が生まれてきたと考えられております。
多種類の使用物質が配合された場合,その効果がそれぞれ単独に用いる場合より増強される事実に対して,ヴィルギの法則(1926)という薬理学上の通則が提唱されています。作用点も作用機構も同じ2種類以上の薬物を混ぜて用いた場合は,その効果は相加されるに過ぎませんが,作用点または作用機構が異なる薬物を混ぜて用いた場合には,その効果は相乗されることがあります。これは薬物の協力作用と呼ばれています。逆に薬物を配合することによって,拮抗作用の現われることもあります。漢方ではこういう薬物の相互作用について,すでに『神農本草経(しんのうほんぞうけい)』序録に7通りに分類しております。つまり単味の作用を単行,助け合うことを相須,協力的な場合を相使,拮抗しあう場合は相反といった組み合わせです。
さて六味丸に桂枝(ケイシ)と附子(ブシ)を加味したものが八味丸(ハチミガン)です。 薬方の成分過程から考えますと,八味丸は『金匱要略』(後漢末)にすでに記載されているのですが,六味丸は宋代銭仲陽(せんちゅうよう)の『小児薬証直訣(しょうにやすしょうじきけつ)』に初めて記載されています。したがって,六味丸は八味丸より桂枝,附子を抜いた薬方であると説明されています。なお八味丸では乾地黄(カンジオウ)が使用されていますか,六味丸では熟地黄(ジュクジオウ)が用いられています。
文献上の記載は今述べましたように,八味丸の方が古いのですが,八味丸の薬効が理解される以前すでに六味丸の薬効がわかっていたであろうと考えるのが妥当でしょう。
八味丸と六味丸の薬効の違いは,明代の名医張介賓(ちょうかいひん)によれば「仲景(ちゅうけい)の八味丸火を益すの剤なり。銭氏の六味丸,すなわち水を盛んにするの剤なり」 と述べています。別の表現をしますと,八味丸は陽虚の薬であり,六味丸は陰虚の薬ということになり,老人には八味丸,小児には六味丸というわけです。銭氏の六味丸を与える証は次のようです。「それ人の命は腎を以て主となし,六味丸は水を盛んにして火を抑制するの剤なり。もし腎が虚して発熱し,口渇を訴え,小便淋瀝して閉し,痰が咽喉につまり,咳嗽吐血し,頭重眩暈し,耳鳴,耳聾,弱視,咽燥痛み,口舌瘡し,歯堅固ならず,腰脚痿弱,五臓虚損し,自汗,盗汗,便血,諸血およそ肝経不足の証,もっともこれを用うべし,けだし水よく木を生ずる故なり。これ水泛(うか)んで痰となるの生薬,血虚発熱の神剤であり,また肝腎の生血不足して虚熱,床に立つことあたわざるを治す」とあります。
■薬能薬理
さて六味丸の君薬は地黄です。地黄は『神経本草経』上品に収載されています。 その修治の方法によって,生地黄(ショウジオウ),乾地黄,熟地黄に分類されております。日本薬局方では,乾地黄,熟地黄の2つは,外観は異なりますが,成分的にはマンニットとして大差がないため,両者を地黄としてまとめて規定しています。生地黄は保存に耐えませんので,薬用には使用されておりません。中国では修治によって薬効は異なるとされています。つまり乾地黄は清熱,涼血に,熟地黄は補血,滋陰に適しているとして,虚寒証には熟地黄,熱証には乾地黄を用いています。この見解によれば,六味丸は乾地黄を用いて,八味丸には熟地黄を用いた方がよいということになります。
地黄は消化吸収を抑制しますので,胃腸機能が弱い人,食欲不振,下痢傾向の人には与えられないといわれていますが,これにこだわることはないでしょう。補血,強壮,解熱,止血剤として貧血症,虚弱者に用います。古くは経験的に熟地黄は虚端を治す良薬であると述べられています。
臣薬として山茱萸と山薬があります。山茱萸は『神経本草経』に蜀酸棗(ショクサンソウ)の名で掲載されています。滋養,収斂など肝腎の補液作用があります。また酸味を帯びているため,とくに肝に働くとされています。地黄,山薬と協同して頻尿,夜間尿,眩暈,耳鳴,腰,膝の鈍痛などに効果があるとされています。山茱萸は補益力が十分ありますが,薬性はおだやかで,しかも抗菌作用も持っています。さらに血流を促進させるたもの解表効果もあります。
山薬は『神経本草経』上品に,薯蕷(ショヨ)の名で記載されています。 滋養,止瀉,去痰作用があり,一般的な補益の薬物として脾胃の虚証に用いられます。つまり虚労を補い,消化を助け,気分を増し,筋肉を強めます。
以上の3つの生薬が,滋陰の効能があり,六味丸の君臣の剤としての三補の薬物です。これに清熱涼血作用の牡丹皮,清熱利水作用の沢瀉,利水剤の茯苓の3者が佐使剤として六味丸を構成しています。
牡丹皮は『神経本草経』中品に記載されています。方剤書では『傷寒論』より以前に現わされたと考えられる『武威医簡』(後漢前期)にも牡丹皮が配剤された薬方があります。しかし『傷寒論』には桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン),大黄牡丹皮湯(ダイオウボタンピトウ),温経湯(ウンケイトウ),八味丸,鼈甲煎丸(ベッコウセンガン)の5つの処方のみに配合されています。吉益東洞(よしますとうどう)は『薬徴(やくちょう)』で牡丹皮が君薬になっている方剤がないため,「主治は不明である」と述べています。当帰(トウキ)や川芎(センキュウ)についても主治を省略しています。桃仁(トウニン)に至ってはいっさい記述されていません。
こうした駆瘀血薬は,現在の漢方診療で多用されているにもかかわらず, 実証の瘀血には牡丹皮,桃仁,虚証の瘀血には当帰,川芎としか分類されていません。最近の薬理実験によって,漢代以降の本草書に記載されている薬能が徐々に解明されて、立証されつつあります。こうした面から逆に瘀血の病理も推測されています。牡丹と芍薬はともにボタン科ボタン属の多年性植物で,前者は根皮を,後者は根を薬用にしています。牡丹皮の主成分はpaeonol,芍薬の主成分はpaeoniflorinであり,互いにそれらを共有しています。したがって,薬効も比較的似ています。消炎作用は牡丹皮が優れ,抗痙攣による鎮痛作用は芍薬が優れていることが推測できます。
薬能から見ますと,芍薬は補血と鎮痛が主体になり,牡丹皮は消炎,涼血が主体になります。この牡丹皮の涼血しながら,血行を促進する効能は,桂枝と併用することによって一層高まります。この働きは八味丸とか桂枝茯苓丸に応用されています。牡丹皮の清熱,涼血,活血して瘀血を去る働きにより,午後に高くなる発熱に用います。
沢瀉は『神経本草経』中品に記載されています。李時珍(りじちん)はこの薬効を「水を去ることを瀉といい,沢水が瀉(そそ)ぐがごとし」と述べていますように,利水作用です。沢瀉と同様に利水作用を有するものに茯苓とか猪苓(チョレイ)があります。茯苓との比較では,利水作用は共通ですが,茯苓には健脾,強壮,鎮静作用があるのに対し,沢瀉には内の熱をさます作用があります。したがって沢瀉は熱状を有する陽証の場合によいわけです。つまり清熱、利水作用といえます。古人は沢瀉が消渇(糖尿病でしょうか)に効果があると述べています。最近の動物実験でも,沢瀉に血糖降下作用のあることが明らかにされています。しかし臨床上,沢瀉を糖尿病の主薬としては使用しておりません。
茯苓は『神経本草経』上品に記載されています。『史記(しき)』には伏霊とあり,松の神霊の気が伏結したものという意味です。利水,滋養,鎮静作用がありますが,ジギタリスに似た強心作用もあります。
■古典・現代における用い方
古代の中国人にとって体の理解は,近代西洋医学における解剖学的臓器とはまったく異質の考え方です。生体を漠然と陰と陽といった立場で観察しています。陰は水,陽は火ともいえます。生体の中で水と火が平行してバランスを保っている状態が健康です。水に対して相対的に火が多過ぎる病態が陰虚であり,六味丸証になります。体の中に火が燃えあがるために熱を感じます。特に腰から熱い感じが起こってきます。腎から生じた水が少なくて,火が燃えあがっている病態ですから,陰虚火動ともいっています。これとは逆に,火に対して相対的に水が多過ぎますと,腰から下が冷えやすくなる陽虚証であり,八味丸の適応です。
古代の中国人にとって腎は水を主り,五臓六腑の生を受けて,これを臓すると考えています。つまり腎は生体の水分を主宰するということで,現代医学の腎(niere)の働きに似たものを考えています。さらに腎は,それ自身の活動に必要は精気を有するだけでなく,五臓六腑からそれぞれの精気を受けて,合わせてこれを蔵するというわけです。
つまり、西洋医学的に考えてみますと,代謝の中心である肝(liver)の働きを腎で行っていたと誤解していたのではないかと考えさせられます。生体の中で相対的に火が水より多いとか,少ないといった考え方は,近代西洋医学的な立場ではほとんど説明できません。
しかし実際の臨床では,こうした立場で病人を見ておりますと,それなりに納得てきる場合が少なくありません。たとえば,ちょっと疲労して休養が必要だと感じている時に,どうしても働かなければいけないということで無理をしますと,腰から足が熱く感じてきます。過労した時には,足蹠から下肢,腰が熱くなるわけです。これが陰虚火動の徴候と見ています。休養すればよいのでしょうが,さらに無理を重ねますと,出血しやすくなります。
こういう病態に六味丸がよく効きます。こういう病態を病名的に考えてみますと,肺結核の初期症状によく似ているように思います。何となく体がだるくと,ほてってくる,いわゆる休の熱感です。また頭がボーッとして,思考力が減退し,腰から膝にかけてだるくて仕方がない,のどが乾いて寝汗が出やすいなどといった徴候です。結核の治療では,洋の東西を問わず,古くは難儀したわけですが,ごく初期に十分な栄養とともに六味丸を与えれば多分よかったのではないかと考えています。
六味丸は,6味の薬物の配合作用により,陰虚火動,つまり慢性消耗性疾患,慢性炎症に見られる発熱,口渇,小便頻数,浮腫,盗汗,眩暈などを目標に与えられらます。銭仲陽が六味丸を用いた目標は,小児の泉門閉鎖遅延,足の発育の悪い歩行遅延,歯の生えるのが遅い,あるいは言語の遅れなど腎虚証です。婦人に多く見られる慢性の腎盂腎炎,腰痛にも有効です。腎盂腎炎の場合,抗生剤がまず用いられていますが,慢性化して抗生剤を使いにくい時に,清熱,消炎作用のある六味丸を使用します。高熱の時には知母(チモ)と黄柏(オウバク)を加えた知柏六味丸(チハクロクミガン)はよく効く薬です。
【副作用】
1) 重大な副作用と初期症状
特になし
2) その他の副作用
消化器: 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢
[理由]
本剤には地黄(ジオウ)が含まれているため、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等の消化 器症状があらわれるおそれがある。
また、本剤によると思われる消化器症状が文献・ 学会で報告されている。
[処置方法]
原則的には投与中止にて改善するが、病態に応じて適切な処置を行うこ
<加味>杜仲(陽)、枸杞子(陰)
右帰丸<補>熟地、山薬、肉桂、附子
<瀉>-、-、-
<加味>鹿角膠(陽)、菟絲子(陽)、途中(陽)、枸杞子(陰)
すなわち六味丸・八味丸から瀉の部分を去り、これにそれぞれ補陰および補陽の薬味を加えている。各薬味の後の(陰) (陽)はそれぞれ補陰、補陽を表わすが、陰陽双補のものは主とする方をとった。そしてここにみられるように、腎陽の補にも決成て補陽剤だけに偏らず、補陰剤を適当に混ぜて、あるバランスを保つよう工夫しており、これが中国における陰陽の考え方だと思われる。
なお飲即ち煎剤より丸剤の方が薬味が多く、より復雑になっているが、このことについて中国では一般に急性病には吸収の早い煎剤を、慢性病には丸剤や膏剤をいわれる練り薬を用いる傾向があり、そして一方、急性病には、大剤といって薬味の種類が少なく、一味一味の量の多いものを用い、慢性病には小剤といって、薬味の種類が多く、一味一味の量の少いものを用いるとされ、これらのことから一般に丸薬には多種の薬味が含まれていることが多いようである。左帰・右帰の飲と丸二組の各々の適用を考える際には、こういった面からの検討も必要なように思われる。
※『小児薬証直抉』? 『小児薬証直訣』の誤りか?
『■重連処方解説(84)』
六味丸(ロクミガン)・牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)
日本東洋医学会評議員 三谷和合
■六味丸・出典・構成生薬
六味丸(ろくみがん)は,地黄(ジオウ),山茱萸(サンシュユ),山薬(サンヤク),牡丹皮(ボタンピ),沢瀉(タクシャ),茯苓(ブクリョウ)の6味からできている処方です。
漢方で使用する薬方のほとんどが,いくつかの生薬の組み合わせによるものです。したがって,こうした薬方の成立過程を考えた時,まず単味生薬の薬効の知識があったはずです。続いて2味の薬効,薬剤の知識があり,さらに3味,4味と加味された薬効の知識があって,漢方が生まれてきたと考えられております。
多種類の使用物質が配合された場合,その効果がそれぞれ単独に用いる場合より増強される事実に対して,ヴィルギの法則(1926)という薬理学上の通則が提唱されています。作用点も作用機構も同じ2種類以上の薬物を混ぜて用いた場合は,その効果は相加されるに過ぎませんが,作用点または作用機構が異なる薬物を混ぜて用いた場合には,その効果は相乗されることがあります。これは薬物の協力作用と呼ばれています。逆に薬物を配合することによって,拮抗作用の現われることもあります。漢方ではこういう薬物の相互作用について,すでに『神農本草経(しんのうほんぞうけい)』序録に7通りに分類しております。つまり単味の作用を単行,助け合うことを相須,協力的な場合を相使,拮抗しあう場合は相反といった組み合わせです。
さて六味丸に桂枝(ケイシ)と附子(ブシ)を加味したものが八味丸(ハチミガン)です。 薬方の成分過程から考えますと,八味丸は『金匱要略』(後漢末)にすでに記載されているのですが,六味丸は宋代銭仲陽(せんちゅうよう)の『小児薬証直訣(しょうにやすしょうじきけつ)』に初めて記載されています。したがって,六味丸は八味丸より桂枝,附子を抜いた薬方であると説明されています。なお八味丸では乾地黄(カンジオウ)が使用されていますか,六味丸では熟地黄(ジュクジオウ)が用いられています。
文献上の記載は今述べましたように,八味丸の方が古いのですが,八味丸の薬効が理解される以前すでに六味丸の薬効がわかっていたであろうと考えるのが妥当でしょう。
八味丸と六味丸の薬効の違いは,明代の名医張介賓(ちょうかいひん)によれば「仲景(ちゅうけい)の八味丸火を益すの剤なり。銭氏の六味丸,すなわち水を盛んにするの剤なり」 と述べています。別の表現をしますと,八味丸は陽虚の薬であり,六味丸は陰虚の薬ということになり,老人には八味丸,小児には六味丸というわけです。銭氏の六味丸を与える証は次のようです。「それ人の命は腎を以て主となし,六味丸は水を盛んにして火を抑制するの剤なり。もし腎が虚して発熱し,口渇を訴え,小便淋瀝して閉し,痰が咽喉につまり,咳嗽吐血し,頭重眩暈し,耳鳴,耳聾,弱視,咽燥痛み,口舌瘡し,歯堅固ならず,腰脚痿弱,五臓虚損し,自汗,盗汗,便血,諸血およそ肝経不足の証,もっともこれを用うべし,けだし水よく木を生ずる故なり。これ水泛(うか)んで痰となるの生薬,血虚発熱の神剤であり,また肝腎の生血不足して虚熱,床に立つことあたわざるを治す」とあります。
■薬能薬理
さて六味丸の君薬は地黄です。地黄は『神経本草経』上品に収載されています。 その修治の方法によって,生地黄(ショウジオウ),乾地黄,熟地黄に分類されております。日本薬局方では,乾地黄,熟地黄の2つは,外観は異なりますが,成分的にはマンニットとして大差がないため,両者を地黄としてまとめて規定しています。生地黄は保存に耐えませんので,薬用には使用されておりません。中国では修治によって薬効は異なるとされています。つまり乾地黄は清熱,涼血に,熟地黄は補血,滋陰に適しているとして,虚寒証には熟地黄,熱証には乾地黄を用いています。この見解によれば,六味丸は乾地黄を用いて,八味丸には熟地黄を用いた方がよいということになります。
地黄は消化吸収を抑制しますので,胃腸機能が弱い人,食欲不振,下痢傾向の人には与えられないといわれていますが,これにこだわることはないでしょう。補血,強壮,解熱,止血剤として貧血症,虚弱者に用います。古くは経験的に熟地黄は虚端を治す良薬であると述べられています。
臣薬として山茱萸と山薬があります。山茱萸は『神経本草経』に蜀酸棗(ショクサンソウ)の名で掲載されています。滋養,収斂など肝腎の補液作用があります。また酸味を帯びているため,とくに肝に働くとされています。地黄,山薬と協同して頻尿,夜間尿,眩暈,耳鳴,腰,膝の鈍痛などに効果があるとされています。山茱萸は補益力が十分ありますが,薬性はおだやかで,しかも抗菌作用も持っています。さらに血流を促進させるたもの解表効果もあります。
山薬は『神経本草経』上品に,薯蕷(ショヨ)の名で記載されています。 滋養,止瀉,去痰作用があり,一般的な補益の薬物として脾胃の虚証に用いられます。つまり虚労を補い,消化を助け,気分を増し,筋肉を強めます。
以上の3つの生薬が,滋陰の効能があり,六味丸の君臣の剤としての三補の薬物です。これに清熱涼血作用の牡丹皮,清熱利水作用の沢瀉,利水剤の茯苓の3者が佐使剤として六味丸を構成しています。
牡丹皮は『神経本草経』中品に記載されています。方剤書では『傷寒論』より以前に現わされたと考えられる『武威医簡』(後漢前期)にも牡丹皮が配剤された薬方があります。しかし『傷寒論』には桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン),大黄牡丹皮湯(ダイオウボタンピトウ),温経湯(ウンケイトウ),八味丸,鼈甲煎丸(ベッコウセンガン)の5つの処方のみに配合されています。吉益東洞(よしますとうどう)は『薬徴(やくちょう)』で牡丹皮が君薬になっている方剤がないため,「主治は不明である」と述べています。当帰(トウキ)や川芎(センキュウ)についても主治を省略しています。桃仁(トウニン)に至ってはいっさい記述されていません。
こうした駆瘀血薬は,現在の漢方診療で多用されているにもかかわらず, 実証の瘀血には牡丹皮,桃仁,虚証の瘀血には当帰,川芎としか分類されていません。最近の薬理実験によって,漢代以降の本草書に記載されている薬能が徐々に解明されて、立証されつつあります。こうした面から逆に瘀血の病理も推測されています。牡丹と芍薬はともにボタン科ボタン属の多年性植物で,前者は根皮を,後者は根を薬用にしています。牡丹皮の主成分はpaeonol,芍薬の主成分はpaeoniflorinであり,互いにそれらを共有しています。したがって,薬効も比較的似ています。消炎作用は牡丹皮が優れ,抗痙攣による鎮痛作用は芍薬が優れていることが推測できます。
薬能から見ますと,芍薬は補血と鎮痛が主体になり,牡丹皮は消炎,涼血が主体になります。この牡丹皮の涼血しながら,血行を促進する効能は,桂枝と併用することによって一層高まります。この働きは八味丸とか桂枝茯苓丸に応用されています。牡丹皮の清熱,涼血,活血して瘀血を去る働きにより,午後に高くなる発熱に用います。
沢瀉は『神経本草経』中品に記載されています。李時珍(りじちん)はこの薬効を「水を去ることを瀉といい,沢水が瀉(そそ)ぐがごとし」と述べていますように,利水作用です。沢瀉と同様に利水作用を有するものに茯苓とか猪苓(チョレイ)があります。茯苓との比較では,利水作用は共通ですが,茯苓には健脾,強壮,鎮静作用があるのに対し,沢瀉には内の熱をさます作用があります。したがって沢瀉は熱状を有する陽証の場合によいわけです。つまり清熱、利水作用といえます。古人は沢瀉が消渇(糖尿病でしょうか)に効果があると述べています。最近の動物実験でも,沢瀉に血糖降下作用のあることが明らかにされています。しかし臨床上,沢瀉を糖尿病の主薬としては使用しておりません。
茯苓は『神経本草経』上品に記載されています。『史記(しき)』には伏霊とあり,松の神霊の気が伏結したものという意味です。利水,滋養,鎮静作用がありますが,ジギタリスに似た強心作用もあります。
■古典・現代における用い方
古代の中国人にとって体の理解は,近代西洋医学における解剖学的臓器とはまったく異質の考え方です。生体を漠然と陰と陽といった立場で観察しています。陰は水,陽は火ともいえます。生体の中で水と火が平行してバランスを保っている状態が健康です。水に対して相対的に火が多過ぎる病態が陰虚であり,六味丸証になります。体の中に火が燃えあがるために熱を感じます。特に腰から熱い感じが起こってきます。腎から生じた水が少なくて,火が燃えあがっている病態ですから,陰虚火動ともいっています。これとは逆に,火に対して相対的に水が多過ぎますと,腰から下が冷えやすくなる陽虚証であり,八味丸の適応です。
古代の中国人にとって腎は水を主り,五臓六腑の生を受けて,これを臓すると考えています。つまり腎は生体の水分を主宰するということで,現代医学の腎(niere)の働きに似たものを考えています。さらに腎は,それ自身の活動に必要は精気を有するだけでなく,五臓六腑からそれぞれの精気を受けて,合わせてこれを蔵するというわけです。
つまり、西洋医学的に考えてみますと,代謝の中心である肝(liver)の働きを腎で行っていたと誤解していたのではないかと考えさせられます。生体の中で相対的に火が水より多いとか,少ないといった考え方は,近代西洋医学的な立場ではほとんど説明できません。
しかし実際の臨床では,こうした立場で病人を見ておりますと,それなりに納得てきる場合が少なくありません。たとえば,ちょっと疲労して休養が必要だと感じている時に,どうしても働かなければいけないということで無理をしますと,腰から足が熱く感じてきます。過労した時には,足蹠から下肢,腰が熱くなるわけです。これが陰虚火動の徴候と見ています。休養すればよいのでしょうが,さらに無理を重ねますと,出血しやすくなります。
こういう病態に六味丸がよく効きます。こういう病態を病名的に考えてみますと,肺結核の初期症状によく似ているように思います。何となく体がだるくと,ほてってくる,いわゆる休の熱感です。また頭がボーッとして,思考力が減退し,腰から膝にかけてだるくて仕方がない,のどが乾いて寝汗が出やすいなどといった徴候です。結核の治療では,洋の東西を問わず,古くは難儀したわけですが,ごく初期に十分な栄養とともに六味丸を与えれば多分よかったのではないかと考えています。
六味丸は,6味の薬物の配合作用により,陰虚火動,つまり慢性消耗性疾患,慢性炎症に見られる発熱,口渇,小便頻数,浮腫,盗汗,眩暈などを目標に与えられらます。銭仲陽が六味丸を用いた目標は,小児の泉門閉鎖遅延,足の発育の悪い歩行遅延,歯の生えるのが遅い,あるいは言語の遅れなど腎虚証です。婦人に多く見られる慢性の腎盂腎炎,腰痛にも有効です。腎盂腎炎の場合,抗生剤がまず用いられていますが,慢性化して抗生剤を使いにくい時に,清熱,消炎作用のある六味丸を使用します。高熱の時には知母(チモ)と黄柏(オウバク)を加えた知柏六味丸(チハクロクミガン)はよく効く薬です。
【副作用】
1) 重大な副作用と初期症状
特になし
2) その他の副作用
消化器: 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢
[理由]
本剤には地黄(ジオウ)が含まれているため、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等の消化 器症状があらわれるおそれがある。
また、本剤によると思われる消化器症状が文献・ 学会で報告されている。
[処置方法]
原則的には投与中止にて改善するが、病態に応じて適切な処置を行うこ